『功利主義論』サポートページ企画です。今回はロバート・オウエンについて取り上げます。
また一方で、オウエン氏は、すべての処罰は正しくないと主張する。というのは、犯罪者は自分の性格や自分の教育を自分で作ったのではないし、彼を犯罪者にならしめた、彼を取り巻く環境を自分で作ったのでもない。それらについて、彼には責任はないのだと。(『功利主義論』)
ロバート・オウエン(Robert Owen, 1771–1858)はイギリスの実業家にして思想家、社会改革家。サン゠シモン、フーリエと並んで、マルクス以前の初期社会主義者として知られています。
オウエンの生涯
オウエンは、イギリス、ウェールズのニュータウンで生まれ、10歳で学校を離れたのち、リンカンシャーのスタンフォードで布地商の見習いとして働き始めました。その後、マンチェスターに移って紡績業に従事するようになり、20歳の頃にはすでに紡績工場の管理者となっていました。
1800年、オウエンはスコットランドのニューラナークにある紡績工場の経営に参画します。この工場は当時、旧経営者のデイヴィット・デイルの開明的な施策によって、ある程度、労働環境や生活条件、児童労働などが改善されていたものの、この工場を社会改革の実験場と位置づけたオウエンは、さらなる労働者の生活と教育の改善に取り組みます。
しかしパートナーたちとの対立が顕在化し、工場の所有権が競売にかけられる事態となります。オウエンは新たなパートナーを集め、その中にはベンサムも名を連ねていました。ベンサムは1株1万ポンド(現在の価値でおよそ8,000万〜1億円)を拠出したとされています。

オウエンは、労働環境の改善、労働時間の短縮、児童労働の廃止を実現し、労働者の生活水準向上や工場労働者の子供たちのために幼児学校を設立するなど、模範的な改革を実施しました。これらにより、オウエンは国際的な注目を集め、理想的な工場経営者として知られるようになりました。
1825年にはアメリカ・インディアナ州において、「ニューハーモニー」と呼ばれるユートピア的共同体を設立します。資本主義の競争を排除し、平等と協力に基づく社会を目指した壮大な社会実験でしたが、経済的困難や内部対立によりわずか4年で解体に至りました。
1830年代には、労働運動や協同組合運動を積極的に支援します。彼は、全国労働組合大連合(Grand National Consolidated Trades Union)の設立を後押ししたほか、労働者による共同経営のストア設立を推進しました。この協同組合運動は後に「ロッチデール原則」として結実し、出資の平等、民主管理、教育の重視、利益の公正配分など、現代の協同組合の基本理念へと発展していきます。
晩年も執筆や講演を続け、自身の社会改革思想の普及に努めましたが、宗教批判を強めたことで多くの反発と批判を受けることにもなりました。
オウエンの「強すぎる」環境決定論
オウエンの社会改革の基本前提にあったのは、環境決定論でした。オウエンは、ジョン・ロックの「白紙説(tabula rasa)」やデイヴィッド・ハートリーの連合主義心理学の影響を受け、人間の性格や行動は生まれながらではなく、教育や経験、環境によって培われるという「性格形成の原理」を唱えます。
問題となるのは、オウエンの「強すぎる」環境決定論です。彼は、人間の性格や行動がほぼ完全にその人を取り巻く環境によって決定されるという極めて強い決定論的思考を持っており、遺伝などの先天的要因を否定するのみならず、自由意志によって選択したと考えられる行為でさえも、環境によって規定されるものであると主張しました。これらは、個人の主体性や道徳的責任を否定するものであり、宿命論や必然論と呼ばれるものと選ぶところがありませんでした。
ミルを呪縛した環境決定論
ミルとオウエンの間に直接的な交流はありませんでしたが、ウィリアム・トンプソンなどのオウエン主義者の主催する公開討論会に、哲学的急進派の仲間とともに参加していた時期があり、非常に有意義な時間であったようです。ミルはオウエンの理想を完全に肯定しますが、相容れない部分もありました。そのひとつがこの強すぎる環境決定論です。この考えは、ミルの哲学の根幹を揺るがすものであり、しかもそれがミル自身も依拠する連合主義心理学を根拠のひとつとしていたため、ミルを呪いのように縛り続け、「寝ても覚めても頭から離れなくなった」というほど、彼を苦しめます。
熟考の末に辿り着いた考えをミルは『論理学体系』第六巻に「自由と必然について」と題した章にまとめています。ありがたいことに、この章は岩波文庫版『功利主義』(関口正司訳)に付録として収録されています。
ここでミルは「必然」という言葉が誤解の元なのだと言います。「人間の性格や行動は環境によって必然的に決定される」という言い方は、物理法則のような絶対的な因果性を持つものではありません。にもかかわらず、「必然」という言葉は、継起の斉一性や予言可能性ということ以上に、いかなる抵抗も変更も受け付けないという、不可抗性を含意してしまっているのです。
しかし人間は自らの環境に手を加えることができる以上、環境決定論に負うとしても変更不可能とまでは言えません。また、変更したいという願望を持ち、それが可能と考えること自体が、道徳的自由なのであり、性格の惰性に逆らって、低俗な快楽を退け、高級な快楽を選び取るというのは、「徳をしっかりとそなえている人だけが完全に自由だ」という言葉の正しさを示す、とミルは考えました。
そうしてミルは「環境決定論と宿命論の間に一線を引き、誤解を招きやすい『必然』という言葉は一切使わないことにした。こうして正しく理解すれば、もう意気消沈させられることはない。私は悩みから解き放たれ」た、と考えるようになりました(『ミル自伝』)。
参考文献
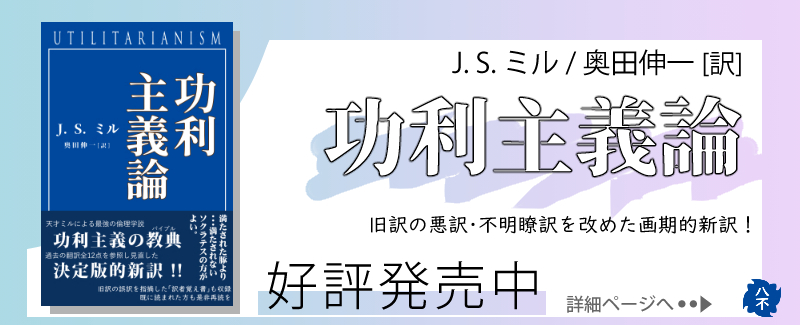

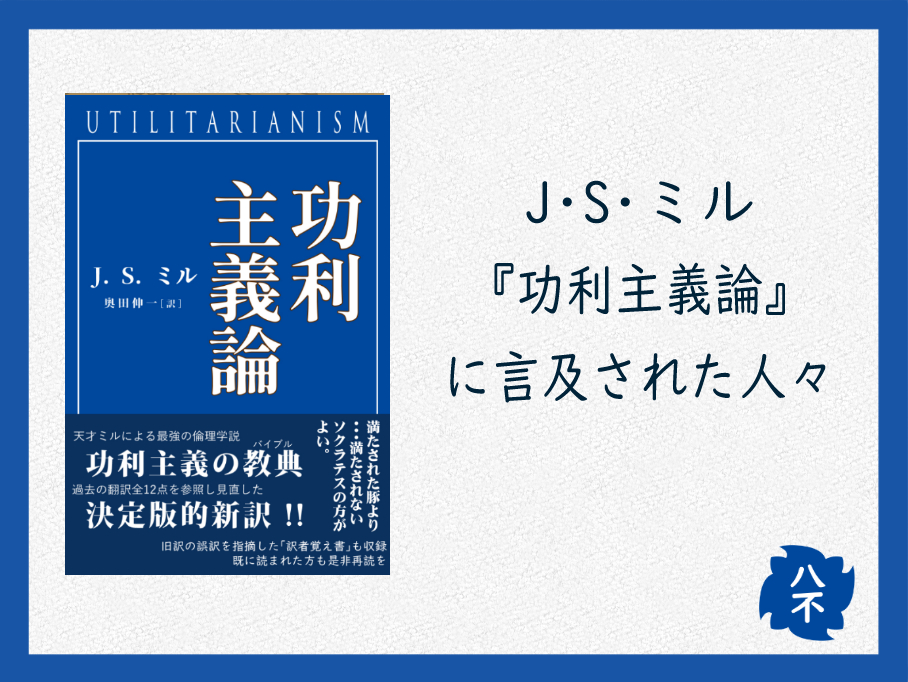


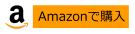

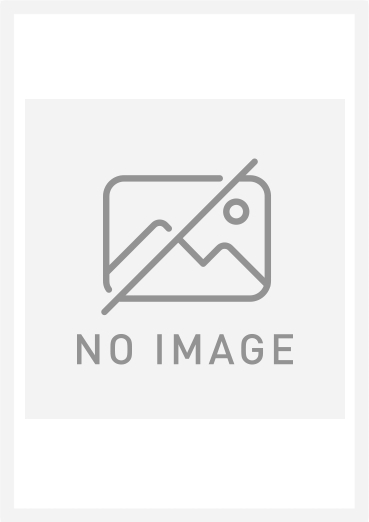



コメント