『功利主義論』サポートページ企画「『功利主義論』に言及された人々」の第14回、最終回です。
功利主義体系の第一原理である、人々の間の完璧な公平という、この含意について、ハーバート・スペンサー氏は、(氏の著作『社会静学』において)功利主義が、正義への十分な手引きとはならない証拠であるとした。(『功利主義論』)
ハーバート・スペンサー(Herbert Spencer, 1820-1903)は、イギリスの哲学者、社会学者です。父は教師でしたが、正規の学校教育はほとんど受けず、父と叔父から博物学や数学、哲学などを教わる家庭学習と独学によって育ちました。
はじめ土木技師として鉄道建設に従事しますが、のちにジャーナリストとして活動を始め、政治や哲学についての論考を執筆するようになります。初期の主要著作である『社会静学』(1851)は高く評価されました。
またスペンサーは、ダーウィンの進化論の影響を受けて、社会を一種の有機体と捉え、社会進化を説く進化論的社会学を確立します。スペンサーは、ダーウィンの「自然選択理論」を「適者生存」(Survival of the Fittest)と表現し、この言葉はダーウィン自身によっても採用されました。
個人主義と自由市場経済の擁護、政府の干渉の最小化を求めるなど、19世紀の自由主義思想を代表する人物の一人でしたが、社会進化論がのちに社会ダーウィニズムと同一視されて、不平等や人種優越論を正当化するものと誤認され、あるいはそうでなくとも、自然科学における進化論を社会に直接適用することの妥当性を疑問視され、批判を受けるようになりました。ただ、この辺りの事情についてはさらに複雑な問題もあり、詳しくは後述します。
『社会静学』における功利主義批判とは何だったのか?
スペンサーは『社会静学』第二編第五章第三節の註において次のように述べます。
We need not here debate the claims of this maxim. It is sufficient for present purposes to remark, that were it true it would be utterly useless as a first principle; both from the impossibility of determining specifically what happiness is, and from the want of a measure by which equitably to mete it out, could we define it.
この格言〔最大多数の最大幸福〕の主張についてここで議論する必要はない。現時点での目的において重要なのは、仮にこの格言が真実であったとしても、それが第一原理として全く役に立たないであろうという点である。なぜなら、幸福とは何かを具体的に定義することが不可能であること、そして仮に定義できたとしても、それを公平に測定する基準が欠如しているからである。
これに対し、ミルは『功利主義論』の雑誌掲載時に、註記内で反論します。これを読んで非常に驚いたスペンサーはミルに手紙を送ります。この手紙を『ミル著作集』などは、スペンサーの『自伝』に収録されているものと同定しており、そこにはこう書かれています。
I have never regarded myself as an Anti-utilitarian. My dissent from the doctrine of Utility as commonly understood, concerns not the object to be reached by men, but the method of reaching it. While I admit that happiness is the ultimate end to be contemplated, I do not admit that it should be the proximate end.
私は自分を反功利主義者と見なしたことは一度もありません。功利主義という教義に対する私の異議は、人間が目指すべき目的そのものではなく、その目的を達成する方法に関するものです。私は幸福が最終的に目指すべき究極の目的であることを認めていますが、それが直接的な目標であるべきだとは認めていません。
スペンサーは、功利主義が幸福の達成に関して「経験的な一般化」のみに頼っており、演繹的推論を欠いていると言います。彼はこのことを説明するために、古代の天文学と現代の天文学の違いを例に出します。古代の天文学は、天体の位置や運動に関する観測の蓄積でしかなかったのですが、それでも蓄積された観測データから、ある時点で特定の天体が特定の位置にあるだろうと経験的に予測できるようになります。これに対し、現代の天文学は重力の法則からの推論によって、天体が特定の時点で特定の位置にある理由を示します。
つまり、古代の天文学は経験的なアプローチ(帰納法)であり、現代の天文学は理論的なアプローチ(演繹法)であると言えます。功利主義は、どのような行為が幸福をもたらすのかについて、経験的なアプローチしか行っておらず、理論的なアプローチが行われていないとスペンサーは主張します。
これに対してミルは、功利主義が理論的なアプローチを軽視しているということはないということ、ただし、ある行為が「必ず」幸福を生み出すといった法則はないということを述べます。両者の相違は見た目ほど大きくないように思われます。
スペンサーはダーウィニストだったのか?
ところで本題とは外れますが、スペンサーに関しては、彼が本当にダーウィニストであったのか、について重大な疑義が提出されています。千葉聡『ダーウィンの呪い』は、スペンサーの社会進化論が実のところ、ダーウィンの自然選択理論に基づくものではなく、「ラマルクの獲得形質の遺伝や進化理神論などで代表される、伝統的なエヴォリューションの観点から導かれたものであ」り、「ダーウィン以前の進化観に基づいて、壮大なスケールで思想を展開した、最後の古典的進化思想家だったのである」と見なします。
それどころか、スペンサー自身、適者生存をあまり重視しておらず、植物のような、あまり“進歩”してない段階の生物に限って作用するものと考えていたのです。
ダーウィンは「自然選択」という概念と、スペンサーの「適者生存」という概念を同一視することに懐疑的でしたが、(自然選択説の共同発表者であった)ウォレスの勧めもあり、妥協的に「適者生存」という言葉を受け入れます。
しかし、不幸にもこの言葉は、やがて弱肉強食の思想や、植民地主義の正当化に利用されていきます。スペンサー自身は植民地主義に批判的であったにも関わらず、勃興しつつあった欧州列強の植民地支配を正当化する原理として悪用されていったのです。
スペンサーの適者生存の思想は、皮肉にも、ダーウィン以後の進化論を導入したと誤解されることによって普及するとともに、批判の的となり、衰退していったのでした。
参考文献
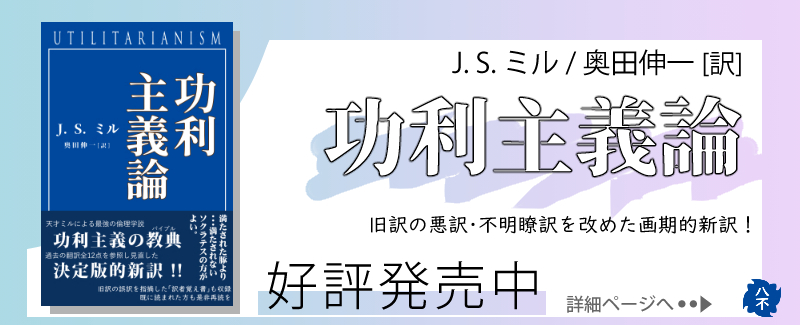

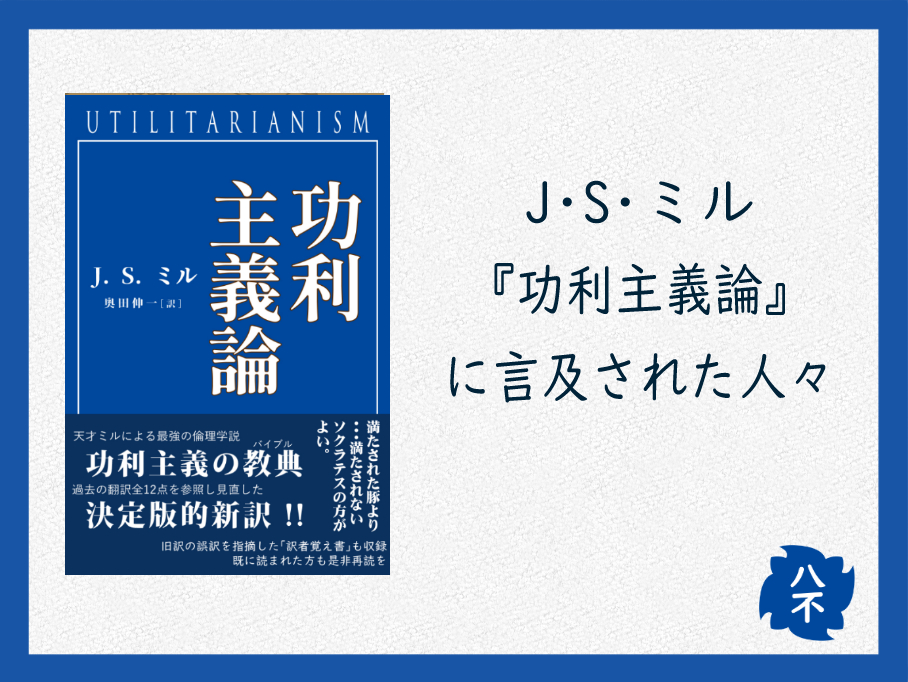


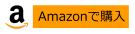

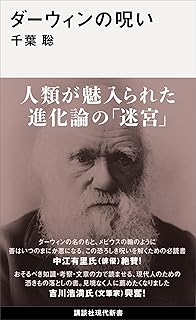

コメント