ジョン・B・トンプソン(久保美代子訳)『ブック・ウォーズ──デジタル革命と本の未来』を読みました。
ここ十数年の本を取り巻く劇的な環境変化を余すところなく書き記そうとする著者の意気込みに圧倒されるような、非常に浩瀚な大著で、やや冗長なきらいがなくもないのですが、興味深く読み進めました。
本書の主題は、まさに我々がその渦中にある、電子書籍や電子書籍リーダーの隆盛であったり、Googleの図書館プロジェクトであったり、Amazonの市場独占であったり、Kindle Unlimitedのような本のサブスクサービスであったり、セルフパプリッシング(自費出版)であったり、Audibleのようなオーディオブックであったり、(日本でいう)カクヨムのような小説投稿サイトであったり──といった、非常に多岐にわたる事象です。
著者の筆致は、個々の話題についても、非常に丁寧かつ丹念に追っていくもので、これらの問題にまったく不案内な向きにとっても、その歴史と全貌が掴めるかと思います。
ただそれが冗漫に感じなくもないというのも事実で、むしろ興味深いのは、著者の独自の分析が光る部分ではないかと思います。例えば、著者は、なぜ、紙の書籍から電子書籍への流れは、思ったほど進まなかったのか?という問いを投げかけます。我々がよく目にする言説では、紙の書籍はどんどん売れなくなって、電子書籍の市場規模はどんどん大きくなっている、というものではないでしょうか。著者の見方は少し違います。
アメリカの大手出版社において、総売り上げに占める電子書籍の割合は、2006年に約0.1%だったものが、年を追うごとに上昇し、2012年には25%近くにまで達します。ところが2013年から2014年にかけて急速にブレーキがかかり、横ばいか減少へと転じたのです。
このことは、ちょうど音楽業界において、CDが配信にとって代わられたことと比べてみると、その現象の特異性がわかるかと思います。出版業界は音楽業界と同じようにはならなかったのです。
著者はその理由についていくつもの考察を与えますが、具体的には本書に当たってもらうとして、著者が力説するのはむしろ、出版界に訪れたデジタル化の波とは、電子書籍によるもののみならず、もちろんAmazonによるeコマースによるもののみでもなく、それらは「私たちの社会で起きているもっと深くてもっと重大な変革のひとつの徴候にすぎない」ということです。
出版業界のファクターである、著者、出版社、流通、小売(あるいは読者も)に、再定義を迫るのが、この「ブック・ウォーズ」とも呼ぶべき大変革の本質ではないかという気がしました。

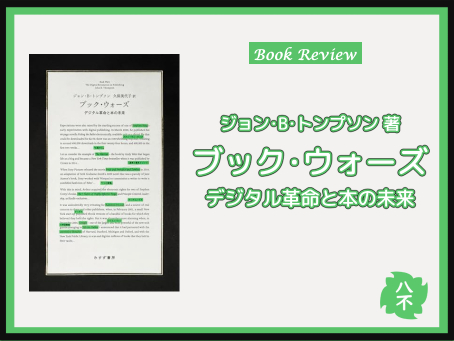
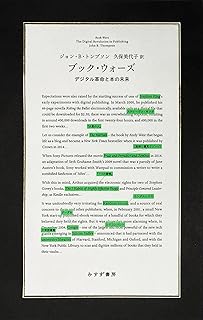
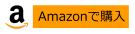



コメント