『功利主義論』サポートページ企画。J・S・ミルの『功利主義論』に言及された人々について解説しています。
「だから、もし先の意図〔幸福の追求〕が空想的であるならば、後の意図〔不幸の防止あるいは緩和〕の有効範囲はますます大きくなるだろうし、その必要性は避けられないものとなるであろう。少なくとも人類が、生きるに値すると考える限り、そしてある条件の下でノヴァーリスが推奨しているような集団自殺行動へと逃避しない限り、そうである。」(『功利主義論』)

ここで言及されているノヴァーリスとは、ドイツロマン主義の詩人・小説家・思想家であるノヴァーリス(Novalis, 1772-1801)です。
「ノヴァーリスが推奨しているような集団自殺行動」という表現はおそらく、ミル自身がノヴァーリスの著作から見出したものではなく、トマス・カーライルのエッセイ「ノヴァーリス」から引いたものと推察されます。カーライルは次のように述べています。
That theory of the human species ending by a universal simultaneous act of Suicide, will, to the more simple sort of readers, be new. As farther and more directly illustrating Novalis’s scientific views, we may here subjoin two short sketches, taken from another department of this Volume.
Thomas Carlyle “Novalis”
(一斉集団自殺行動による人類終焉の理論は、素朴な読者にとっては斬新に映るだろう。ノヴァーリスの科学的見解をさらに直接的に示すために、この書物の別の部分から短いスケッチを2つ付け加えることにする。)
では、当のノヴァーリス自身は、どのように述べているか。このような表現が直接用いられている文章はありませんが、例えば『ザイスの弟子たち』という著作では、次のように語られています。
「この憐れむべき人類の傍に、さながら一個の救い主のように立っているのが死である。なぜなら、死がないとすれば、最も気のちがった者が、最も幸福なわけだから。(……)すべての人間が共同の一大決心によって、この苦境から、この恐るべき牢獄から自己を解きはなち、現世の所有物をみずからすすんで断念することによって、彼らの種族を永遠にこの苦悩から解放して、一段と幸福な世界、彼らのなつかしい父祖の国にまで救い出すべき、あの偉大な時期が来なくてはすまぬであろう。こうして人間は自分にふさわしい最後を遂げて、暴力的な必然の抹殺や、それ以上にも恐ろしい、思考器官の漸次的な破壊や狂気による動物への堕落を、未然に防ぐであろう」
ノヴァーリス「ザイスの弟子たち」(『信仰と愛』山室静訳、青磁社、1947年)
このような記述は、さも自殺志願者や反出生主義者による厭世的な文章のように読め、こういった記述がカーライルに、人類の一斉集団自殺行動を推奨していると解釈させたことは想像に難くありません。ところが、ノヴァーリスが通常の意味で厭世家であったか、また文字通りの意味で、人類の一斉集団自殺を推奨していたか、については疑問の残るところです。以下では、そのあたりの事情について述べたいと思います。
ゾフィーへの愛と自殺願望
ノヴァーリスは、筆名で、本名をゲオルク・フィリップ・フリードリヒ・フォン・ハイデンベルクといい、1772年に生まれ、1801年、29歳の若さで結核のため、夭逝しました。ゲーテは彼を、ドイツの精神生活の「最高司令官(インペラトール)」になれたはずであり、なるべきだった人間と評したといいます。
彼の人生において、ロマン派の思想家たちとの出会いと同じくらい重要だったのが、ゾフィーとの出会いです。ノヴァーリスは、ゾフィー・フォン・キューンという少女に一目惚れし、のちに婚約しますが、この時、ゾフィーはわずか12歳でした。
しかも彼女は重病にかかり、15歳で亡くなってしまうのです。ノヴァーリスはひどく落胆し、ゾフィーを追って死ぬことで、彼女と再会することを切望しました。
しかし、彼のゾフィーへの愛は、次第に観念化し、あたかも聖母マリアを慕うような、信仰へと変化していきます。自殺願望についても、直接的な後追い自殺を求めるというよりも、象徴的な自己放棄や自己超越といった哲学的な行為を意味するものとなっていきました。
その契機となったのが、ゾフィーの墓前で経験した神秘体験でした。彼はそこで、時空を超越してゾフィーとの「再会」を果たすのです。「こうして、私は初めて、夜の天国とその光に、天上の恋人に、永遠に、ゆるがぬ信仰を感じた」。
夜(=死)の讃歌とは
『夜の讃歌』において、ノヴァーリスは、古代の神々が昼と光の神であり、夜と死への恐怖は隠蔽され、それゆえに古代の宗教は死に屈服し、生の明るく照らされた部分を祝うことに専念したのだと語ります。しかし「この愉悦の宴を不安と苦痛と涙で断ち切ったのは死だった」として、キリストの死と夜と復活の体験によって、この世界で初めて死と夜の面を征服し、恐怖を奪ったのだと考えます。ザフランスキー『ロマン主義』はこのことをゾフィーに重ね合わせます。
「実際にノヴァーリスは、ゾフィーがキリストのように自分の先達となって死に赴き、魔術を使い自分を彼岸へと引き連れていくのを経験した。この時に彼は、愛が死の恐怖に打ち克ち、『夜の熱狂』を生み出すことができると体験できた」
つまり、ノヴァーリスにとって夜の讃歌=死の讃歌とは、生を嫌悪し、死に執着するものではなく、死の恐怖の克服と、よりよき生への欲望、そしてそれが愛によってなしうる、ということなのでした。ノヴァーリスはこの過程を(象徴的な)「自己殺害」(Selbsttödtung)として捉えました。
「死によって、生は強められる」
久野昭『魔術的観念論の研究』は、ノヴァーリスが「自殺の決心を、眼に見える客観的な行為に移す代わりに、これをイロニーとしておこなった」と評します。そして「現実の生と死との間隙を烈しく意識しながら、彼は、この間隙を自己の生の中での死によって埋める道を選んだが、実は、この道だけが、彼の生を強める力を持っていた」とし、ノヴァーリスの次の言葉を引用します。
「死は私たちの生をロマンティッシュにする原則である。死はマイナスであり、生はプラスである。──死によって、生は強められる」
そして久野は「アイロニカルではあるが真剣な自殺による自己改造過程が、ゾフィーの死後、ノヴァーリスが自らに課した生き方であった」といいます。
丸山武夫『ノヴァーリス』は、聖母マリアなどの理想像がすべてゾフィーの思い出に溶け込んでひとつのものとなり、墓塚での神秘体験が「時空の制限を脱し、肉体を離れたゾフィーが身近にいることを確信するにいたった」として、「ゾフィーが死んだことは『崇高なる偶然』(himmlischer Zufall)であり、『万能の鍵』(Schlüssel zu allem)となった。『殺人剣』は変じて『魔術的活人剣』となった」と述べています。
『夜の讃歌』の「解説」において、笹沢美明も、ゲーテの『ファウスト』において昇天したマルガレーテがファウストの導き手となったように、ゾフィーがノヴァーリスの導き手となったことにより、「ノヴァーリスはもうゾフィーを追って死のうとは思わず、現世にあって彼女と共に暮らしていたのである」と述べています。
つまり、ノヴァーリスの自殺の観念は、もはや厭世的で悲観的な、死の切望ではなく、死によって生を強める、哲学的な行為となっていきました。ザフランスキーは、「死への憧憬とは実際にはより高められた生への欲望であり、ノヴァーリスは意志の力でそこに到達したいと願い、恋人の変容したイメージに魔術的に惹きつけられ」たのだといいます。
このため、『ザイスの弟子たち』からの先の引用も、生を忌避して、字義通りの「人類の一斉集団自殺」を推奨するものではないと解釈されます。
参考文献
リュディガー・ザフランスキー『ロマン主義 あるドイツ的な事件』(法政大学出版局 2010)
今泉文子『ロマン主義の誕生 ノヴァーリスとイェーナの前衛たち』(平凡社 1999)
久野昭『魔術的観念論の研究』(理想社 1976)
丸山武夫『ノヴァーリス』(世界評論社 1949)
笹沢美明「解説」(『夜の讃歌:他三篇』岩波書店 1959)



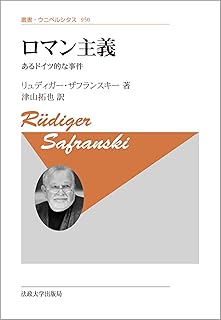




コメント