『功利主義論』サポートページ企画。J・S・ミルの『功利主義論』に言及された人々について解説しています。

「カーライル氏は次のようにこの問いに輪をかける。汝はつい先ほどまで、存在についてさえ何かの権利を持っていたのか。続けて彼らはこう言う。人は幸福がなくともやっていける。高貴な人間なら誰しも、このように感じており、Entsagen〔ドイツ語で「諦める」「断念する」〕、あるいは自制の教訓を学ばなければ、高貴な人間にはなれなかったのである。」(『功利主義論』)
ここで登場する、「カーライル氏」とは、トマス・カーライル(Thomas Carlyle, 1795-1881)、スコットランド出身の社会批評家、思想家です。かつては日本でも本国イギリスでもよく読まれたようですが、近年ではあまり読まれなくなったようです。その原因も含めて、カーライルの人と思想について、特にミルとの関係に注目しつつ、解説したいと思います。
奇書『衣装哲学』
カーライルは石工職人の息子としてスコットランドに生まれました。牧師になるべくエディンバラ大学で学びますが、宗教的懐疑から、牧師になるのを辞めて、教職などを経たのち、文筆業に入ります。『フレイザーズ・マガジン』に掲載された『サーター・リサータス』(邦訳では一般に『衣装哲学』や『衣服哲学』などと訳される)は、ドイツ語混じりの晦渋な文体、小説とも思想書ともつかない奇妙な著作で、当初は必ずしも好評をもって迎えられませんでした。そのため、単行本として刊行されたのも、『フランス革命史』によって一定の評価を得た後のことでした。
この『サーター・リサータス(Sartor Resartus)』とは、英語で言えばテイラー・リテイラード(Tailor Retailored)、すなわち「仕立てし直された仕立て屋」とか「補綴(つぎはぎ)された仕立て屋」という意味のスコットランド語を元に、ラテン語風に造語したものだといいます。
ディオゲネス・トイフェルスドレックという架空のドイツ人哲学者が書いたとされる文章(「衣装哲学」)を、カーライルが編纂したという体裁をとっています。A. L. ルケーンはこの書を「分類も要約も拒む、不思議なロマン主義の傑作」と評しています(『カーライル』)。
先の引用文の”Entsagen”も『サーター・リサータス』に登場します。
Well did the Wisest of our time write: ‘It is only with Renunciation (Entsagen) that Life, properly speaking, can be said to begin.
宣なる哉、現代の最も賢き人が書いたこと。『本来から言つて、人生は唯だ諦念によつてのみ始まると言ふことが出来る』(石田憲次訳『衣服哲学』)
さらに次のような記述もあります。
Foolish soul! What Act of Legislature was there that thou shouldst be Happy? A little while ago thou hadst no right to be at all.
愚かな奴め! おまへが幸福なるべしといふどんな議会の法令があるか。ほんの少し前までおまへは全く存在する権利さへももたなかった。(同上)
ミルは『サーター・リサータス』の原稿を最初に読ませてもらった時には、さっぱり意味がわからなかったが、雑誌に連載され、もう一度読んだ時には、感動し心から称賛したと述べています。
ミルとの出会い
ミルとカーライルとの関係は、奇妙なねじれを持っていたように思われます。
二人の出会いのきっかけは、カーライルがエグザミナー誌に掲載された「時代の精神」と題する匿名論文を読み、「新しい神秘主義者がいる」と快哉を叫んだことに始まります。この論文の著者がミルであることを突き止めたカーライルは、ミルとの面会を果たし、そこでもまた、彼を自分と同じ政治的信念を持つ人物と“確信”するのですが、ここからして既にカーライルの早とちりでした。
この時期、ミルは、コールリッジらのロマン主義の思想に接近していたとはいえ、決して功利主義を手放しておらず、やがてカーライル自身が悟るように、むしろカーライルの批判対象となってもおかしくない人物でした。
ミルの方はというと、カーライルの興奮とは裏腹に、第一印象として、友人に宛てた書簡では、ゲーテなどのドイツの思想家の影響が強く、「彼には独創的な思想がない」と冷ややかな評価をしていました。
ただ、のちに『自伝』では「時代の精神」論文の唯一の効果は、「カーライルと知り合えたことである」と評することになります。カーライルは、ワーズワースやコールリッジなどと並んで、それまでの硬直な人間観に囚われていたミルに、ロマン主義的な要素(論理だけでなく感情の重視)を注入し、より広い見識を与えた人物の一人でした。
原稿焼失事件
カーライルとミル、二人の関係においてよく知られるのが、原稿焼失事件です。ミルはカーライルから『フランス革命史』の出版前原稿を預かるのですが、誤って紙屑入れに入れてしまい、暖炉で燃やしてしまいました。ミルは顔面蒼白になって、カーライルの元に謝罪に訪れ、賠償を申し出ますが、カーライルはむしろミルの憔悴ぶりを気遣い、申し出を断ります。それでもと強く懇願されたため、カーライルは執筆に要した時間の生活費を受け取ることにしますが、それも倹約家のカーライル夫人によって相当減額されたものでした。
この事件は、二人の友情と、(意外にも)寛容なカーライルの人間性を示す良いエピソードなのですが、その裏で、その後の二人への禍根も残しました。それはミルのパートナーであったハリエット・テイラー夫人についてです。
ハリエットを嫌うカーライル
カーライルはこの原稿焼失事件の犯人をハリエット・テイラーであると疑います。ハリエット・テイラーは、のちにミルの妻となる人物ですが、この時まだジョン・テイラーと夫婦関係にありました。イアン・キャンベルは、ハリエットが原稿を無造作に扱い、放置していたため、女中が紙屑と誤って燃やしたと述べていますが(『トマス・カーライル』)、小泉仰は、ミルの妹の手紙などから、やはりミルの手違いが原因であると述べています(『J・S・ミル』)。
カーライルがハリエットを疑った原因の一つは、彼女には夫がありながら、ミルと不倫関係にあるとカーライルには映ったためかもしれません。カーライルはハリエット犯人説を至る所で吹聴し、それを聞きつけたミルがカーライルを遠ざけるようになったとも言われます。
また、カーライルの方でも、ミルに対する当初の共感は薄れて、思想的にはむしろ敵対者であると認識するようになったようです。カーライルにはミルが、悪い意味での現代の申し子であり、冷血な論理計算機のように映っていました。
『フランス革命史』で名声を確立
原稿焼失事件という困難を乗り越え、カーライルは再起して『フランス革命史』を書き上げます。ミルが書評で後押ししたこともあってか、この書によってカーライルは一躍、読書界で一目置かれる人物となりました。
特に『フランス革命史』以降、カーライルの関心は政治や社会に向けられ、その辛辣な社会批評は、多くの読者を獲得し、1840年代には「チェルシーの聖者」と称されることもあったといいます。
「ロマン派の第一世代の詩人たち、ブレイク(32歳)、ワーズワス(19歳)、コールリッジ(17歳)」は、「フランス革命を抑圧からの解放として賞賛した」1という側面もあるようですが、カーライルのフランス革命に対する評価は手厳しく、辛辣でした。彼はフランス革命を「破獄した無政府主義者が、腐敗せる官権に対して公然と暴挙し妄動せる叛逆及び勝利を謂ふのである」と評し、「要するに、フランス革命は、暴言を吐き、狂想を逞しうする暴民の心と頭に在つたのである」と総括しました(『仏国革命史 上巻』高橋五郎訳)。
このため、カーライルは、愚かな民衆に権力与えても意味はないとして、民主主義や代議制に期待することなく、むしろこれを否定して、カリスマ的英雄による独裁を希求するようになります。
このようなカーライルの愚民観と英雄崇拝にミルは反対の立場を取り続けました。カーライルがフランス革命をフランス啓蒙思想の成れの果ての災難と捉え、ドイツ・ロマン主義に傾倒していたのに対し、フランス啓蒙思想の側についたミルという対照は、示唆的なものです。
反動化するカーライル
カーライルの意に反して、イギリス社会が民主化していくにつれ、彼の思想は反動化していくことになります。「黒人問題」と『現代論のパンフレット』は、挑発的以上の問題作であり、端的に差別的かつ反動的な論考でした。
「黒人問題」において、カーライルは、英領西インド諸島の解放奴隷の(牧歌的とされた)暮らしを、堕落した生活と批判し、イギリス人によって使役されて労働するのがよいとする、奴隷制の実質的な復活を主張しました。これに対しミルは直ちに反論文を著し、猛抗議します。しかし翌年の『現代論のパンフレット』においても、自由主義と民主主義への拒絶が貫かれており、これはちょうど『自由論』と『代議制統治論』においてそれらを擁護するミルと正反対の道を歩むことになりました。
それまで、保守派から危険な急進主義者と批判されていたカーライルは、同時に、自由主義者・急進主義者から、反動主義者と批判されるようになりました。そして多くの人から「英国知識階級の偉大な手に負えないご老人」と見なされるようになります(『カーライル』、強調は原文傍点)。
エア総督事件でミルと対立
さらに、エア総督事件では、またしてもミルと激しく対立することになります。エア総督事件とは、英領ジャマイカで起きた原住民による暴動を植民地総督であったエドワード・ジョン・エアが強硬策をもって鎮圧した事件で、この時の対応が人権侵害であるとしてイギリスで大問題となりました。ちょうど下院議員を務めていたミルは、この問題を扱うジャマイカ委員会の委員長を務めることになります。
ミルをはじめ、ダーウィン、ハクスリー、スペンサーらはエア総督糾弾派、一方、カーライルをはじめ、ラスキン、ディケンズらは擁護派として国論を二分した論戦が繰り広げられました。
ミルの訃報に触れて
以上のように、ミルとカーライルの関係は、カーライルの誤解から来た急接近に始まり、ミルにロマン主義思想の影響を与えつつも、次第に対立的になり、疎遠になっていきます。そしてついに1873年、ミルが他界します。訃報を聞いたカーライルは、「なに、ジョン・ミルが死んだって! (……)私が友達を必要としていた頃、彼は私にとって最も友情に厚かった。(……)凡そ人間の中で、彼以上に洗練され、やさしく、感受性が強く、温厚な人間を私は知らない」と述べたと言います(『カーライルとミル』)。
しかしミルの死後に公刊された『自伝』を読んだカーライルはひどく失望することになります。「思慮があり清廉で誠実な人間によって書かれた書物でありながら、これ以上面白くない、いや馬鹿げたと言わねばならぬ──書物を私は読んだことがない。……それは全く理屈をこねる機械(エンジン)の生涯であって、それには、機械化された鉄で出来た物によって送られたとしても、これほどではないと言ってよいほど人間味が足りない」と弟に宛てた手紙に書いています。
死後の評価
一時は、イギリス読書人界で注目を浴びるひとりであったカーライルですが、その死後、ミルに比べて、極端に言及されることの少なくなった人物でもあります。その一因を向井清は次のように述べています。
「第一次および第二次世界大戦が勃発した際には、ビスマルクに端を発したカイザー・ウィルヘルムとアドルフ・ヒトラーへと受け継がれるドイツ軍国主義の先駆けをなす思想家として話題になり、英語圏の世界ではカーライルの名声はいっそう損なわれることになった」(向井清「トマス・カーライル」『文学都市エディンバラ』)
1943年(昭和18年)、すなわち第二次大戦中に出版された榊原巌の『英帝国崩壊の予言者トマス・カーライル』は、その意味で非常に興味深い見方をしています。カーライル的な思想を裏切って発展を遂げたイギリスではあるが、今やイギリスはカーライル的な思想を受け入れた枢軸国側と対立し、カーライルの警告を無視したイギリスを始めとする反枢軸国側は没落して、枢軸国側が勝利することになるだろうというのです。
カーライルの思想の帰結が果たして枢軸国の思想だったのか、慎重な検討を要するとは思いますが、こうした捉え方が今日において、日本でもイギリスでもカーライルが読まれなくなった一因であろうと思われます。
向井は先の引用に続けて、「しかし二〇世紀後半になると、彼の芸術性に関する再評価がなされるようになった」と述べています。ルケーンも「現在において彼の名声がもっとも高いのは文学者としてである」と書いています。
「しかしこれがカーライルの偉大さを主張する根拠であるとするなら皮肉なことである。なぜならカーライルが自分自身の役割として、芸術家以上に猛烈に拒否したものはほとんど何もなかったからである。(……)彼が繰り返し主張していたことであるが、自分が属する不運な世代の著者として、唯一許容できるのは預言者の役割だけであった」(『カーライル』)
参考文献
A. L. ルケーン『カーライル(コンパクト評伝シリーズ 10)』
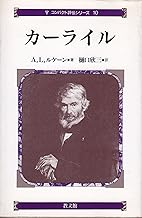
エメリ・ネフ『カーライルとミル:ヴィクトリア朝思想研究序説』

榊原巌『英帝国崩壊の予言者 : トーマス・カーライル』
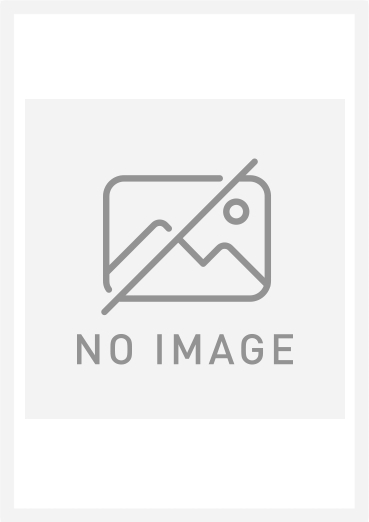
イアン・キャンベル『トマス・カーライル』

向井清「トマス・カーライル─苦悩・回心・愛の道のり─」(『文学都市エディンバラ ゆかりの文学者たち』所収)

矢島杜夫『ミルの『自由論』とロマン主義: J.S.ミルとその周辺』

有江大介(編著)『ヴィクトリア時代の思潮とJ.S.ミル: 文芸・宗教・倫理・経済』

小泉仰『J・S・ミル』

- 泉谷周三郎「第1章 J.S.ミルとロマン主義──ワーズワス、コールリッジ、カーライルとの関わり」(『ヴィクトリア時代の思潮とJ.S.ミル』所収) ↩︎





コメント