『ポストデジタル時代の公共図書館』
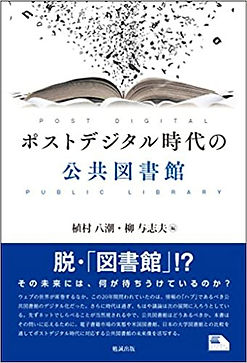
植村八潮・柳与志夫編『ポストデジタル時代の公共図書館』(勉誠出版, 2017)
「電子書籍を切り口にして公共図書館を論じることは、デジタル化時代における公共図書館の役割やあり方を論じることである」(p.2)
この本はまず読み物としてもおもしろかったです。電子書籍の普及によって図書館はどうなる(べき)か、という問題は、常々提起される問題ですが、それは後回しにして、まずは日米の出版業界の違いについて語られた「電子書籍・電子図書館が抱える『下部構造的』課題」(吉井順一)がおもしろい。
アメリカでは出版社が寡占化しており、多くの場合、作家と出版社の間に、エージェントが入ります。エージェントは売れ線を狙いますから、そこからこぼれた、ともかく作品を世に出したい人たちによる、セルフ・パブリッシングが流行しているそうです。(次に紹介する伊藤論文によれば、「2012年には全体の46%を占めていたBig5による書籍の販売点数は、2015年には35%まで減少した一方、2012年には市場の5%に過ぎなかったセルフパブリッシングの販売点数が2015年には12%にまで伸びている」とのことです)
また出版社側では、「電子版の出現以前から、校閲作業やバージョン管理の手間なども含めて総合的に考えると、XMLやXHTMLベースでテキストを中心にした制作を進め、紙にする場合はそれを組版ソフトなどに流し込み、同時に電子配信用の変換も行う」というやり方(つまり電子書籍ベース的なやり方?)があったのですが、これがさらに進んで「極論すれば『在庫ゼロ』へ向かう、製造とインベントリーの融合」が起こっているとのこと。要するに受注生産方式です。
吉井論文でも図書館問題について言及しているのですが、ここでは次の「米国公共図書館の電子書籍サービスの発展」(伊藤倫子)から見ていきたいと思います。アメリカでは9割の図書館で電子書籍の貸出が行われているのですが、ある調査では電子書籍の貸出を行っていることを知っていたのは全体の46%で、実際に借りたことがあるのはそのうちの16%しかいなかったということです。
また、出版社との取り決めにより、電子書籍の貸出にはOne Copy/One Userの制限が設けられており、さらには永久アクセス権を与える代わりに販売価格を紙書籍の3〜4倍に変更したという事例もあるのだとか。
理不尽ではありますが、図書館で同時に何万人にでも新刊が貸し出せるのだとしたら、出版社の商売は成り立たないでしょう。
こうした問題への解決策として、Pay-per-useモデルが提唱され、実行されています。これは要するに、貸出された分だけ出版社(というかプラットフォーム)に支払うというもの。これをさらに発展させたものとして、Pay-as-you-readというものもあって、これは利用者が「読んだ」ページ数分課金されるというものです。
一見すると良さそうではあるのですが……。
「図書館にかける予算は全国平均でひとりあたり40ドル弱、この予算で毎年オンラインショップのギフトカードを買って地域住民全員に配れば、それぞれ欲しい本を自由に買うことはできるだろう。でもそれでは、その地域のために収集し、保存し、共有する知識という財産は育たない」(p.59)
テキサス州ベア郡には、紙の本がない図書館が3館もあるそうで、これはデジタル・ディバイド解消のために、無料Wi-FiやPCが設置されており、電子書籍端末の貸出を行っているそうです。現在でもそうであるはずではあるのですが、図書館が紙の本を貸す場所以上のものとして再定義されていくことになるのでしょう。



コメント